こんにちは、こはるです。
「漢方なら安心」「副作用は少ない」って思っていませんか?
実は私もそう思っていました。
でも、そんな思い込みがきっかけで、体調を大きく崩して救急車を呼んで入院する事態に…
多くの漢方に配合されている甘草(カンゾウ)による怖い副作用の偽アルドステロン症を知っていますか?
漢方薬は自然由来で優しいイメージがありますが、なかには強い作用を持つ成分もあります。
特に「甘草(カンゾウ)」という成分は、多くの漢方に含まれていて、むくみ・高血圧・低カリウム血症を引き起こす原因にもなり得ます。
漢方はドラッグストアで手軽に手に入るものが沢山あります。
これから漢方を飲もうか考え中の方、自分の判断で飲んでいる方は、漢方による副作用について知っておいた方がいいです。
この記事では、私が実際に経験した「偽アルドステロン症」についてお話しするとともに、漢方の副作用リスクや予防のポイントをわかりやすくお伝えします。
健康のために始めた漢方で、体を壊さないために…
ぜひ参考にしてください。
私が経験した偽アルドステロン症について書いた記事▼
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://koharu-happy-days.com/entry/pseudoaldosteronism-chinese-medicine-experience/]
- 偽アルドステロン症・低カリウム血症
- 漢方にも副作用がある
- 自己判断で飲み始めない
- 体面積の小さい人・持病がある人は要注意
[outline]
偽アルドステロン症とは?原因・症状をわかりやすく解説

偽アルドステロン症とは、7割の漢方に配合されているとされる甘草(カンゾウ)の成分=グリチルリチンが原因となって引き起こされる症状
- 血液検査で低カリウムが認められる
- むくみ
- 手足の脱力感・しびれ
- 動悸
- のどの渇き(口渇感)
- 血圧上昇
- 体重増加
- 頻尿または出なくなる などなど
甘草の主成分のグリチルリチンは、美容に関心がある方は知っているかもしれません。グリチルリチン酸ジカリウムと似たようなものです。
グリチルリチン酸ジカリウムには袁紹を抑えるさようなら(抗炎症効果)があり、風邪薬やスキンケア製品など、実にざまな薬に使われています。
薬以外にも調味料などの食品、化粧品や洗眼液など様々な製品に使われています。
[blogcard url=https://tourokuhanbaisha.com/?p=3734]
化粧品の成分表示でも「グリチルリチン酸ジカリウム」は頻繁に見かけます。
になりやすくなってしまうのですが、様々な製品にグリチルリチンが含まれ
ているので、知らぬ間に大量摂取になってしまうということがあります。
甘草を含む漢方を飲むときは、グリチルリチンの総摂取量に注意する必要があります。
難しい発生メカニズムなど詳しいことはこちらに書いてあります。▼
[blogcard url=https://www.min-iren.gr.jp/?p=33878]
こちらのレポートは漢方を服用する患者さんに向けて書かれていて、とても分かりやすく解説されています。▼
https://www.pmda.go.jp/files/000144115.pdf
漢方薬の効果は高いが、副作用にも注意が必要

漢方薬は「効き目が穏やか」「副作用が少ない」といったイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
でも実際は、体の内側にじわじわと作用し、しっかりと効いていくのが漢方の特徴です。
そのため「穏やか=安全」と思い込んでしまうと、副作用に気づきにくくなることもあります。
たとえば、漢方を飲んで不快な症状が和らいできたとき。
その変化がゆるやかすぎて、「体に効いている実感はないけれど、実はしっかり作用していた」ということも珍しくありません。
だからこそ、副作用も同じように、軽い変化から始まり、気づいたときには重い症状になっていることもあるのです。
自己判断で漢方を飲み始めるのは危険?その理由とリスク

漢方は東洋医学での中心的な治療法の1つです。
私は以前、漢方の効果に感動して興味を持ち、この東洋医学の本を読みました。▼
医学と付いてることもあってすごく難しいです。
1度や2度読んだ程度では理解したり、覚えることは難しいです。
日本での医療の基本は西洋医学ですが、東洋医学も一緒に組み込めば、もっともっと良い医療が出来そうなのになと感じました。
あ、ちょっと話が逸れました
漢方はそれぞれの体質や証(しょう)に合わせて処方されます。
患者の体を診察して様々な理論を用いて得られた、体の状態を示す総合評価のこと
漢方を処方するときには、証と言われる体の状態の評価を見極めること(=診断)がとても重要になっています
その証の診断を間違えると、漢方で期待する効果が十分に発揮されません。
その逆もあり、症状が改善するどころか、悪化してしまう事もあります。
そんな難しくて重要な証(体質)の見極めを、素人が自己診断することは、かなり難しいことだと思います。
東洋医学を理解するのはとても難しいのに、漢方はドラッグストアで簡単に手に入れることが出来てしまいます。
それが手軽でありがたい一方、自己判断で選んでしまうと大きなリスクにもつながるのです。
私の経験談でもありますが、自分の治したい症状が書いてあるから・・・という理由だけで飲んでしまう人がほとんどではないでしょうか。それはとても危険なことだと思いました。
漢方の取り入れ方は、きちんと医療関係者、漢方薬局など専門の人に相談してから飲むことが大切です。
体格が小さい人・持病がある人は副作用が出やすい?

高血圧や糖尿病、心疾患などの持病がある場合、副作用が出やすくなることがあります。
持病の薬との飲み合わせの関係もあるので、漢方を飲む際はかかりつけの先生と相談する必要があります。
- 体が小さい人
- 体重の軽い人
一般的な薬でも、大人と子供で処方される薬の量が違うように、漢方でも大人と子供では処方が変わってきます。
体表面積が小さい人は、標準的な体格の人に比べて、偽アルドステロン症などの副作用が起こりやすいとされています。
女性(男性の2倍)や低身長・低体重で体表面積の小さい人、高齢者に生じやすく、利尿剤やインスリン使用患者では低カリウム血症を起こしやすく、重篤化しやすいので注意が必要です
一般的に市販薬の説明には『○○歳以上は~』などと年齢についてが書かれています。その理由は肝機能の成長度合が関係しているとの事です。
つまり、15歳になると一般的には大人とほぼ同じ程度に肝機能が発達するので、大人と同量の薬を飲んでもよいということになっています。
同じ「大人」でも身長や体重には個人差があります。それにもかかわらず、薬や漢方薬を服用する際に体格についての注意書きを見かけることはあまりありません。
私自身、市販の漢方薬で副作用を経験するまで、体格差による服用方法の違いを意識したことがありませんでした。
漢方を含め、市販薬を飲むときに、体格について気にしたことがある人はほとんどいないのではないでしょうか。
小児科では体重を聞かれたりしますが、大人になると聞かれない事の方が多いですよね。
色々と調べている時に、大人とは体重50キロを想定していると書かれた記事を目にしたりしました。
漢方薬の副作用と実際に出る症状まとめ【私の実体験も】

漢方薬による副作用は、甘草(カンゾウ)だけが原因とは限りません。
ほかにも、オウゴン、ケイヒ、トウキなどにも副作用があります。
症状も、偽アルドステロン症だけではありません。
アレルギー、肝機能障害、間質性肺炎など怖い副作用がでる漢方もあります。
小柴胡湯(しょうさいことう)という漢方では、2000年までに41人の死亡例が報告されているそうです。
[blogcard url=https://biz-journal.jp/2017/09/post_20730.html]
副作用から身を守るためにできること【医師に相談すべき?】

市販の漢方薬を『自分の症状に合っているから』『薬よりは良さそう』という安易な気持ちで飲み始めるのは、おすすめしません。
かかりつけ医、薬剤師や専門家に相談する事が大切です。
でも、これも私の経験談から思う事があります。
西洋医学の薬、東洋医学の漢方も重い副作用が出ること自体がまれです。
お医者さんや専門家でも、『そういうことはまれだから心配ないよ』と言われることが多いかもしれません。
実際私もかかりつけ医には、漢方の桂枝加竜骨牡蠣湯(ケイシカリュウコツボレイトウ)を服用している事を伝えていましたが『はいはーい、そうなのねー』とさらりと聞き流されていました。
まれだから・・・と言われても、実際自分の身に、まれに起こる重い副作用が出てしまったら・・・その時点で、もうまれだとは思えなくなります。
相談することはとても大切です。でも、相談したからと言って『安全』が保障されるわけではありません。
体質は人それぞれで違うので、お医者さんでも分からない部分があります。
症状が出て、初めて分かることもあります。
偽アルドステロン症の私の経験談▼
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://koharu-happy-days.com/entry/pseudoaldosteronism-chinese-medicine-experience/]
あくまでも自分の体は自分で守るという考えを持つことが大切です。
自分の体に意識を向けて、異変が起きたら気付けるようにしておくことも大切だと思います。
まとめ:自然=安全と思い込まないで。漢方と正しく向き合うことの大切さ

怖いことをたくさん書いてきてしまいましたが、漢方は上手に使えば、とても優れた治療法だと思います。
漢方を飲むときは、知識として副作用、アレルギー等があることを知っておくだけで、いざという時の対応の仕方が変わってくると思います。
上手に取り入れていきましょう。
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。


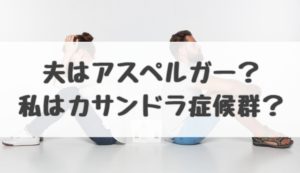


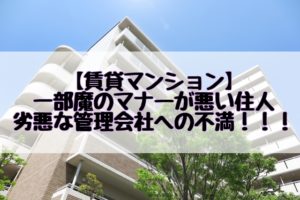
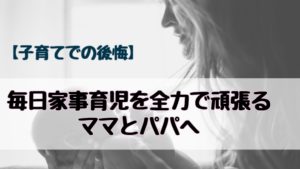


コメント
コメント一覧 (4件)
funyada様♡
コメントありがとうございます✨
後日私の偽アルドステロン症の経験談も書こうと思っています。あんな思いはもうしたくないと思う程、地獄でした。
漢方の服用を検討する際は、必ず専門家などに相談してくださいね。
まさしく「漢方=副作用が少ない」と思ってました!ありがとうございます。
ta-sanpapa様♡
そうですね。処方薬でも副作用の可能性を頭に入れながら飲む方が異変に早く気づけますね。
for-mom様♡
専門的な知識のある人に、きちんと見てもらって、正確な証を決めて処方された漢方が『副作用が少ない』ということなのかなと思いました。市販の漢方を自己判断で飲んだ時は、これに当てはめてはいけない気がします。